栃木県宇都宮市の空間プロデューサーの日々報告
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ようやくこの旅のメイン、茶室について。
茶の湯。室町時代に行われていた闘茶・書院の茶から精神性を志向した珠光。そして堺にて侘び茶を追求した紹鴎。その弟子で、茶の湯を大成させた千利休。弟弟子の薮内剣仲が薮内家を起こし、利休の子孫である少庵、宗旦、宗守等により表千家、裏千家、武者小路千家が興る。さらに古田織部や小堀遠州らが大胆で自由な茶風をあみ出してゆき、、、といったあたりが歴史としての茶の湯の流れです。もちろんここに、信長、秀吉、家康らとその時代性が深く関わってきます。



僕が茶の湯というか、露地や日本庭園にうっすら興味を持ったのは大学時代。
日本建築研修で奈良京都を訪れ、桂離宮と修学院離宮に行った時でした。
建築自体はもとより、気になったのは、そこに至る行程でした。
ここで幅を狭めて視線を絞り、曲がったところで一気に開く。不安定な踏み石を気にさせつつ、いつの間にかまた森の中に。踏み石を変えたり小さい門を潜らせたりして、その先は違うエリアになるんだよ、と伝えつつ、目標の建物へ文字どおり紆余曲折しながら辿り着く。
もちろん寺社建築にもアプローチによる意識の操作は相当仕込まれていて、
伏見稲荷なんかはアプローチ自体が目的になっている、顕著なものです。
その、空間的仕掛けによる身体そして意識の操作性、なんとなくそれに気付いていながらも没入してしまっている自分に気付き、その作為の鮮やかさに気持ち良ささえ感じたことを覚えています。



さらに大学卒業設計時から大学院留学を経て今だに僕の中で研究のテーマとなっている、
「空間と身体の関係性、その種・強度がどのように意識(気持ち)へ影響されるか」
の答えが、現代建築でもギリシアの建築でもなく茶室にあるのではないかという漠然とした仮説が。
浮び上がってきたのは、留学中にクラスメイトに自分の空間に対する考え方を伝えている時。
それまでは、自分の思う真の空間とその捉え方(仮説)は人間にとって根源的なものなので、
万国共通の概念であると考えていました。
共通の概念であることは確信を得たのですが、なにかが違う。
どうやら、この感覚を得る為のプロセスが圧倒的に違うんじゃないか。と感じた時に、
日本固有の空間の関わり方・捉え方が茶室にありそうな気がしました。
茶の湯はものすごく漠然とした世界で、突き詰めれば突き詰める程、凝視すれば凝視する程、焦点をぼかされてしまう。明確な目的がある訳でもなく、フォーマットもはっきりしていない。
しかし、得も言われぬ喜びを得ることができる。なんなんだ、この世界は。
そしてそんな文化が当たり前のように生まれ、定着してる日本は。と思った訳です。


茶の湯は一見、形式ばって堅苦しい、難しいモンだと思います。でも僕の解釈では、あれは只の形式でしかなく、要はどれだけ寛げるか。どれだけ楽しめるか。そしてどれだけ主人やお客の気持ちを汲むか。が重要。それらを成立させる為に、ツールとして流れや茶道具、掛軸などがあるだけで、それらが気持ちの邪魔になったりしたら意味がないわけです。しゃべりたければしゃべればいいし、しゃべりたくなければしゃべらなければいい。結局はどれだけそこに居るお互いが気持ち良く過ごせるか、が大切。というようなことを「美味しんぼ」でノ貫先生が言ってた気がします。
さて茶室です。実に様々なタイプがあります。


<西芳寺(苔寺)湘南亭> <同、潭北亭>


<大徳寺高桐院> <高台寺遺芳庵>



<高台寺時雨亭> <高台寺傘亭> <大徳寺高桐院松向軒>
天井の高いもの、2階にあるもの、暗いもの、明るいもの、すごく狭いもの。
平面的にも、給仕口や床の間、炉、躙口などといった要素があったりなかったり。
見れば見る程、ぼかされていきます。
これらを見て廻り、裏千家会館などでお茶を頂きながらお話を聞いている内に
薄目で見えてきたことがあります。
それを最後の2室で書いてみようと思います。

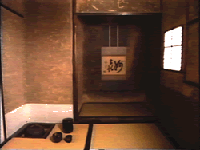
<南禅寺金地院八窓席> <妙喜庵待庵>
八窓席・・・3帖台目、大きな窓、主人-炉-お客の位置関係 等々。
明るく自由、ざっくばらんな雰囲気。
待庵・・・・2帖、小さい下地窓が3つ、炉-主人-お客の位置関係 等々。
狭く暗い。2人だけの緊張感。
細かくあげれば要素の違いはキリがないのですが、
明らかなのは、この2室に居る人達の関係は全く別種だろうな、ということです。
八窓席は数名でわいわいと楽しそう。待庵は2人でじっくりできそう。
主人とお客の元々の関係にもよるので、どちらが良いとは言えないのですが、
要は2者がどのような関係を築きたいか、に尽きると思います。
その為に露地があり、茶室があり、茶道具があり、掛軸があり、所作があり、お茶がある。
それらがひとつの方向に向って「空気」を創り出す。
茶室に関していえば、幅/奥行/天井高さと向き/床の間とその位置/窓による光の調節/炉の位置/給仕口の位置・大きさ/素材と、空間を構成する要素は多岐に渡りますが、
その全てが「築きたい2者の関係性」という目的に向っているんです。
なるほど。「関係性」「空気」か。見ようとしても見えないはずです。
でもその、「空気をかもし出し」「空気を察する」という能力は日本人の特殊な能力のはず。
そこに少なからず関われる、空間づくりというのはやっぱ面白いです。
茶の湯。室町時代に行われていた闘茶・書院の茶から精神性を志向した珠光。そして堺にて侘び茶を追求した紹鴎。その弟子で、茶の湯を大成させた千利休。弟弟子の薮内剣仲が薮内家を起こし、利休の子孫である少庵、宗旦、宗守等により表千家、裏千家、武者小路千家が興る。さらに古田織部や小堀遠州らが大胆で自由な茶風をあみ出してゆき、、、といったあたりが歴史としての茶の湯の流れです。もちろんここに、信長、秀吉、家康らとその時代性が深く関わってきます。
僕が茶の湯というか、露地や日本庭園にうっすら興味を持ったのは大学時代。
日本建築研修で奈良京都を訪れ、桂離宮と修学院離宮に行った時でした。
建築自体はもとより、気になったのは、そこに至る行程でした。
ここで幅を狭めて視線を絞り、曲がったところで一気に開く。不安定な踏み石を気にさせつつ、いつの間にかまた森の中に。踏み石を変えたり小さい門を潜らせたりして、その先は違うエリアになるんだよ、と伝えつつ、目標の建物へ文字どおり紆余曲折しながら辿り着く。
もちろん寺社建築にもアプローチによる意識の操作は相当仕込まれていて、
伏見稲荷なんかはアプローチ自体が目的になっている、顕著なものです。
その、空間的仕掛けによる身体そして意識の操作性、なんとなくそれに気付いていながらも没入してしまっている自分に気付き、その作為の鮮やかさに気持ち良ささえ感じたことを覚えています。
さらに大学卒業設計時から大学院留学を経て今だに僕の中で研究のテーマとなっている、
「空間と身体の関係性、その種・強度がどのように意識(気持ち)へ影響されるか」
の答えが、現代建築でもギリシアの建築でもなく茶室にあるのではないかという漠然とした仮説が。
浮び上がってきたのは、留学中にクラスメイトに自分の空間に対する考え方を伝えている時。
それまでは、自分の思う真の空間とその捉え方(仮説)は人間にとって根源的なものなので、
万国共通の概念であると考えていました。
共通の概念であることは確信を得たのですが、なにかが違う。
どうやら、この感覚を得る為のプロセスが圧倒的に違うんじゃないか。と感じた時に、
日本固有の空間の関わり方・捉え方が茶室にありそうな気がしました。
茶の湯はものすごく漠然とした世界で、突き詰めれば突き詰める程、凝視すれば凝視する程、焦点をぼかされてしまう。明確な目的がある訳でもなく、フォーマットもはっきりしていない。
しかし、得も言われぬ喜びを得ることができる。なんなんだ、この世界は。
そしてそんな文化が当たり前のように生まれ、定着してる日本は。と思った訳です。
茶の湯は一見、形式ばって堅苦しい、難しいモンだと思います。でも僕の解釈では、あれは只の形式でしかなく、要はどれだけ寛げるか。どれだけ楽しめるか。そしてどれだけ主人やお客の気持ちを汲むか。が重要。それらを成立させる為に、ツールとして流れや茶道具、掛軸などがあるだけで、それらが気持ちの邪魔になったりしたら意味がないわけです。しゃべりたければしゃべればいいし、しゃべりたくなければしゃべらなければいい。結局はどれだけそこに居るお互いが気持ち良く過ごせるか、が大切。というようなことを「美味しんぼ」でノ貫先生が言ってた気がします。
さて茶室です。実に様々なタイプがあります。
<西芳寺(苔寺)湘南亭> <同、潭北亭>
<大徳寺高桐院> <高台寺遺芳庵>
<高台寺時雨亭> <高台寺傘亭> <大徳寺高桐院松向軒>
天井の高いもの、2階にあるもの、暗いもの、明るいもの、すごく狭いもの。
平面的にも、給仕口や床の間、炉、躙口などといった要素があったりなかったり。
見れば見る程、ぼかされていきます。
これらを見て廻り、裏千家会館などでお茶を頂きながらお話を聞いている内に
薄目で見えてきたことがあります。
それを最後の2室で書いてみようと思います。
<南禅寺金地院八窓席> <妙喜庵待庵>
八窓席・・・3帖台目、大きな窓、主人-炉-お客の位置関係 等々。
明るく自由、ざっくばらんな雰囲気。
待庵・・・・2帖、小さい下地窓が3つ、炉-主人-お客の位置関係 等々。
狭く暗い。2人だけの緊張感。
細かくあげれば要素の違いはキリがないのですが、
明らかなのは、この2室に居る人達の関係は全く別種だろうな、ということです。
八窓席は数名でわいわいと楽しそう。待庵は2人でじっくりできそう。
主人とお客の元々の関係にもよるので、どちらが良いとは言えないのですが、
要は2者がどのような関係を築きたいか、に尽きると思います。
その為に露地があり、茶室があり、茶道具があり、掛軸があり、所作があり、お茶がある。
それらがひとつの方向に向って「空気」を創り出す。
茶室に関していえば、幅/奥行/天井高さと向き/床の間とその位置/窓による光の調節/炉の位置/給仕口の位置・大きさ/素材と、空間を構成する要素は多岐に渡りますが、
その全てが「築きたい2者の関係性」という目的に向っているんです。
なるほど。「関係性」「空気」か。見ようとしても見えないはずです。
でもその、「空気をかもし出し」「空気を察する」という能力は日本人の特殊な能力のはず。
そこに少なからず関われる、空間づくりというのはやっぱ面白いです。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
最新情報
当社も入居するシェアオフィスが2010年4月スタートしました。入居希望の方、連絡下さい。
ユニオン通りにてフリーペーパー制作室を開設。編集&製作協力者、募集中です。
最新TB
プロフィール
HN:
taisei
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
宇都宮のこと、栃木のこと、街のこと、ロンドンのこと、建築のこと、不動産のこと、空間のこと、身体のこと、機能のこと、美術のこと、音楽のこと、映画のこと、妄想のこと、無駄なこと、予期しない出会い/組合せのこと、なんでもないモノゴトに惹かれます。
ブログ内検索
